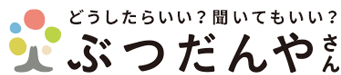ためになる!?ぶつだんやさんコラム
2020年9月29日
「捨てられる宗教」を読んで
- お仏壇と墓石の太田屋
- 太田博久(代表取締役)
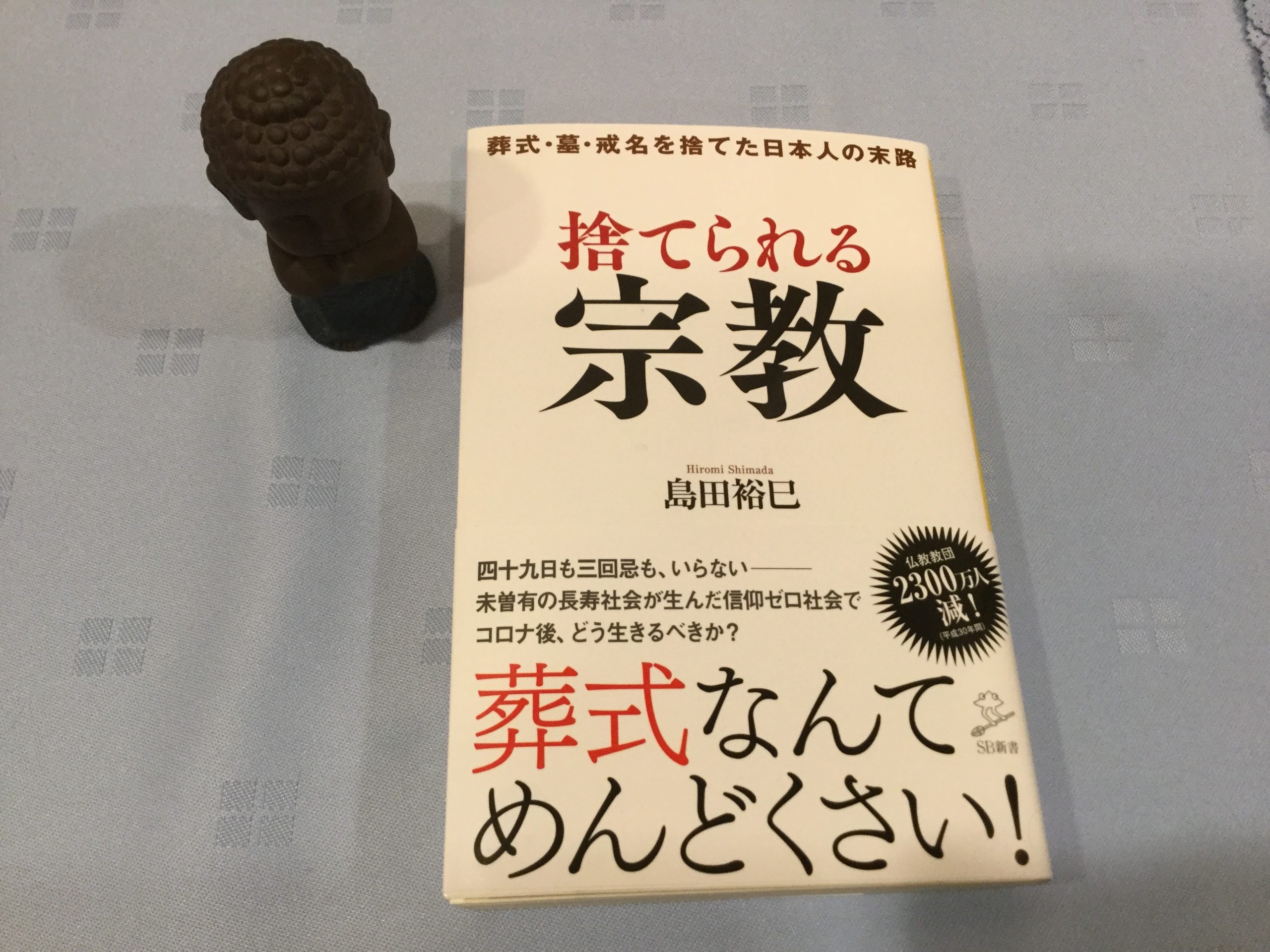
2010年に新書「葬式は、要らない」が30万部のベストセラーになった、宗教学者島田裕巳さんの新刊「捨てられる宗教」を読みました。日本に限らず、経済発展を遂げ、平均寿命が延びている先進諸国ではイスラム教を除くどの宗教においても、この30年間で軒並み統計上の「信者数」が激減している実態から、その原因と今後の生き方について言及した内容です。
島田さんによると、日本では、平成の30年間で神道系で約30%減、仏教系で約45%減、そして高度経済成長期に激増した新宗教でも同様に「信者数」の減少が確認できるそうです。その原因を島田さんは「死生観の転換」にあると言っています。
そもそも、ある程度体系化された宗教が発生し発展した(信者数が増加した)時代は、人間が「いつまで生きられるかわからなかった」時代であった。多くの不治の病、戦争、災害、そして基本的な生存条件を満たすだけの経済生活状態が不十分だった時代では、子どもをはじめ、若い人が亡くなることも多く、平均寿命が今より随分短かった時代であり、その中で人間が持っていた「死生観A」が宗教を受け入れる重要な素地であった。その死生観は、生きること自体に基本的な困難が伴い、人々はそれから逃れられる来世(天国・極楽浄土等)への生まれ変わりを期待し、その死生観が宗教の発展を支えていた、と島田さんは言います。
ところが、先進国では、医療技術の発達、経済発展による基本的生存条件の向上等により平均寿命は急激に延び続けていて、「人生100年」どころか「人生110年」時代を迎えています。人間が長年「いつまで生きられるか」と思いながら生きていた状況から、「いつまでも生きられる」「なかなか死なない、死ねない」とも言える状況となり、人生が「スケジュール化」され、「死の意味」が大きく変化してきたことで「死生観B」の時代への転換が起きている。つまり「死生観B」とは、たとえば自分が「90歳ぐらいまで生きるだろう」と想定し、終わりから逆算して人生を「スケジュール化」して捉える死生観だと言います。それが「来世での救い」を無力化し、宗教の必要性を大きく減退させているのではないか、との論点が提示されていると私は捉えました。
確かに、葬送や供養の仕事に携わる私も、最近のお葬式やお仏壇やお墓を巡る変化の背景に、いわゆる「宗教離れ」とも思える現実が潜んでいるように感じています。そして、その仕事を営む人間だからこそ、もしそうであるなら、受け入れがたい現実であっても決して逃げずに現実を直視し、対処していかなければならないと思っています。ただ、それがこの本の副題にある「葬式・墓・戒名を捨てた日本人の末路」や、帯に記載された「葬式なんてめんどくさい!」「四十九日も三回忌も、いらない…」という言葉と直接結びつけられることには大きな違和感を持たずにはいられません。もちろん、本のタイトルは内容以上に刺激的につけられるものでしょうし、この本で島田さんが書いている内容も、「死生観が転換」している時代にどう生きていくのかに力点が置かれているとは思います。それを承知した上でも私が違和感を持つのは、この「死生観の転換」の論点の基礎が「1人称の死」の視点だけに偏っていて、「2人称の死」や「3人称の死」からの視点が抜け落ちているのではないかと考えるからです。
ここで言う「1人称の死」とは「私にとっての私の死」を指し、「2人称の死」とは「私にとってのあなた(夫・妻・両親・子ども)の死」、「3人称の死」とは「私にとってのあの人(友人知人・同僚・仲間)の死」を指します。葬送や供養に携わる私が日々接するのは、亡くなられた故人ご本人ではなく、ご遺族であり、故人の友人や仲間の方々です。その方々と接していると、どなたにも故人への大切なお別れの気持ちがあり、それぞれに悲しみや痛みを抱えている事実に直面し、葬送も供養も、その形をつくる大きな要素は、その気持ちのあり方だと強く感じています。そして、一人ひとりの死生観(どう生き、どう死ぬのか)も、決して自分自身(1人称)の視点から捉えただけのものではなく、ご家族の死(2人称)、友人や仲間の死(3人称)からの視点をも包み込んだ死生観になっているのではないかと思うのです。
私は学者ではありませんので、統計データに基づいているわけでもなく、感覚レベルでの捉え方に過ぎないかもしれません。それでも、お葬式やお仏壇やお墓に表れる葬送や供養の形は、やはり亡くなった故人ご本人の死生観以上に、ご遺族や友人や仲間の死生観が、故人の死に対し、「1人称」の視点からだけで捉えた死生観を越えて発動されるものではないかとの「確信」があるのです。
葬送や供養の仕事に携わりながらも、私も私自身の死を考えたときには、どう送ってもらおうと、どう供養してもらおうと、正直に言えばある意味「どうしてもらっても構わない」と思っています。でも、妻や子ども達がどう考え、どう感じ、どう送ろうとするのかは、当然私が思う形とは異なるだろうと思います。そこには、私が私の死を捉えた場合の死生観ではなく、妻や子ども達が持つ死生観が、他者である私の死に対して発動されるはずです。それが、葬送や供養を形づくる大きな要素に他なりません。
亡くなられた故人がもし「死とは無である」と捉えていたとしても、残されたご遺族や友人・仲間といった生前共に生きてきた方々の死生観の発動は、故人はきっと「お仏壇の中にいる」「お位牌に魂がある」「お墓で会える」「千の風になっている」「山や海や空にいる」という「きっと、どこかにいて、見守ってくれている」と確かに感じ、今でも間違いなく信じている、あるいは信じたいと思っている姿として現れています。それが宗教学者の島田さんの言う、宗教の定義する「天国」や「浄土」という「来世」とは異なっていたとしても、かけがえのない大切な人を亡くされた方々の紛れもない死生観の反映ではないか、と私には思えるのです。
島田さんがこの本に書かれている内容の本質とはズレてしまった気もしますが、たとえ形は変わったとしても、葬送や供養は人間にとって大切な営みだと信じる私が、もしかしたら過度に刺激的につけられた副題や帯の言葉に強く反応してしまっているだけかもしれません。でも、これは、私がこの「捨てられる宗教」を読んで率直に感じ、考えたことです。
島田さんの言う「死生観の転換」が起き始めているのだとすれば、それは宗教にとっても、葬送や供養にとっても、また人間そのものにとっても大きな出来事だと思います。人間の死生観に関係の深い仕事に携わる人間として、これからもこの「転換期」について考え続けていきたいと思います。